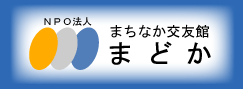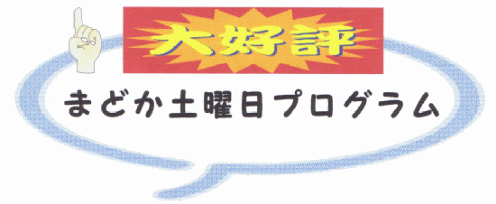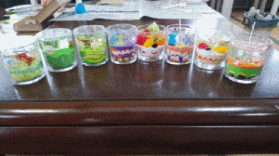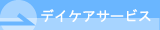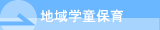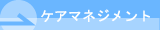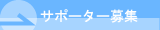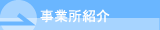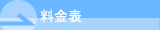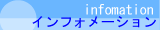まちなか交友館まどかは認知症と診断されたご本人の日中活動を支援します。(つくば市北条)
土曜日プログラム日記
Vol.88 (2019/12/21) 蕎麦打ち
| 蕎麦打ち教室は10回目。 まどかで一番「伝統ある」行事です! |
 |
|
 |
 |
 |
Vol.87 (2019/11/9) りんごジャム
 |
今年も来てくださいましたマツジュンさん。 マツジュンさんといえば、もはや『定番』のりんごとサツマイモ(^^) 大子町特産のりんごをたくさん持ってきてくださって、 ちょっとスパイシーなりんごジャムを作りました。 |
 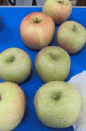 |
左側の大きいのが「陸奥(むつ)」 その隣が「王林(おうりん)」 奥に3つ見えるのは「ふじ」 右側のは「秋映(あきばえ)」 そのまま食べると陸奥はちょっと モソモソした感じ、秋映は美味 でした。 |
 |
 |
|
| リンゴを煮ている間に、ホットケーキを焼きました。 甘〜い匂いが漂って、期待が高まるばかりです。 |
  |
 |
リンゴの食感が残るくらいが美味しい、とのことで ボリュームも満点なジャムが出来上がりました。 |
 |
早速試食会。 甘すぎずスパイシーなジャムは いくらでも食べられます。 リンゴの食べ比べもしてみて、 種類によって特徴があるのも よくわかりました。 マツジュンさん、 今年もありがとうございました! |
 |
Vol.86 (2019/7/13) メルトビーズ&ヨナナス
 |
今年も変わらずに来てくださった梨枝子さんと力さん。 工作もスイーツも、と欲張ってリクエストしたら、バッチリ応えてくださいました。 |
  |
  |
 で、次のお楽しみはデザート 「ヨナナス」って・・・?? 凍らせた果物を専用のミキサーで潰してシャーベット状に したもの、です。 バナナで有名なメーカーが作った機械で、音がうるさいとか、 手入れが面倒とかであんまり流行らなかったらしいんだけど、 100%果汁シャーベットが美味しくないわけはありません。 作って、食べて、楽しいひとときでした!! |
|
Vol.85 (2019/4/14) いちご大福&抹茶ティラミス
| パティシエの和(より)さんに「いちご大福を作りたい」 とリクエストしたら快く引き受けてくださいました。 「大福だけじゃ物足りないからもう一品」とおねだりしたら 抹茶ティラミスを作ろうとのこと。
|
 |
| ティラミスはマスカルポーネというチーズと 生クリーム、卵を合わせて作ります。 マスカルポーネはねっとりしてるから なめらかなるまでに練るのが大変でした。 |
 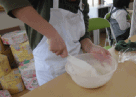 |
 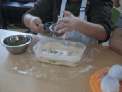 |
スポンジケーキを抹茶の液に浸したものと、 クリームとを二層にして、抹茶を茶こしで漉し ながらふりかけたらできあがり。 冷蔵庫で冷やします。 |
| で、今度は本題の大福作り。 ティラミスを作っている間に小豆が煮え、あんこができました。 1個分ずつ丸めてイチゴを包みます。パティシエがやるとクルクルっと簡単そう なのに、ベタベタするしイチゴがはみ出すし、悪戦苦闘してしまいました。 |
 |
| 大福の皮は白玉粉を水で溶き、レンジでチン して作ります。あんこより更に包むのが難しかっ たけど、特大のイチゴ大福ができあがりました。 ティラミスも大福も、ペロっとたいらげ至福の時 を過ごしたのでした〜!! |
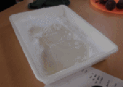  |
Vol.84 (2019/2/16) ぼたもち
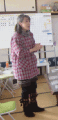 |
これまた恒例、菊池美和子先生による ”伝統郷土料理シリーズ” 今回は、ぼたもちを作りました。 季節や地域によって「ぼたもち」とか「おはぎ」 などと呼ばれます。牡丹と萩の花が由来だとか・・・ |
 |
| 餅米とうるち米を合わせて炊いたものを、麺棒でつぶして 「半殺し」にします。 ちょっと物騒な呼び方だけど、餅米が粒状でもなく餅状でもない 「半分つぶれた状態」がいいのです。 温かいうちにやらないと、うまくつぶれてくれません。 |
 |
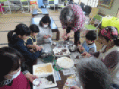  |
モチっとした感じになったら、俵型にまるめます。 うるち米のおにぎりよりも、ちゃんとまとまるから 子ども達も上手にできました。 |
| きなこやゴマをからめたり、 あんこでくるんだり。 手のひらにラップ乗せ、餡を広げてやると きれいにくるむことができました。 |
 |
 |
お待ちかねの試食タイム。 甘さ控えめだから(ってただの言い訳!) いくつも食べられちゃいます。 中にこしあんを詰めて、ゴマをからめたのも好評でした。 ひと昔前は、おばあちゃんが重箱にたくさん作って くれたものだ、なんていうお喋りをしながらワイワイ いただきました。 |
Vol.83 (2018/12/16) 蕎麦打ち
 |
恒例の蕎麦打ち教室。 師匠の久松さんと飯島さんが、 いつもと変わらずに来てくださいました。
|
| 今年は、台風の影響で蕎麦の 出来があまり良くないとのこと。 でも、挽きたての新蕎麦粉は香り がいいし、はじめは遠巻きにしてた 子ども達も、その手触りの良さに どんどん引き込まれていきました。 |
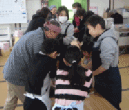  |
 |
何回やっても難しいのは、薄く四角くのばすところです。 師匠がやるとまるで魔法のように広がります。 室内の乾燥状態や蕎麦粉の状態、水加減等によって ちぎれてしまったりもするのです。奥が深いですね・・・ |
| 挽きたて・打ちたて・茹でたて のお蕎麦は美味しいに決まっています!! 皆お腹一杯食べたのは言うまでもありません。 師匠、今度は10回目。 また来年もよろしくお願いいたします。 |
 |
Vol.82 (2018/11/24) 大学いも
| 土曜日プログラム講師の皆さまとは、「年に1回だけお会いする」 のが通例になってしまっていますが、この方もそうです。 マツジュンさん。 作業療法士なのですが、利用者さん達の就労を支援するために様々 な工夫をし続けていて、今はリンゴの『研究』をしていらっしゃいます。 |
 |
 |
地元で作っているリンゴを加工して商品化し 障害者の”安定収入”を確保しようと言う試みを しているとのこと。頑張ってほしいものです。 ところで、今回の食材はさつまいも! |
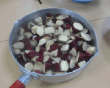 |
| 紅はるかです。 お芋のお菓子の王道をいく、大学芋 を作りました。 乱切りにしてじっくり揚げてタレをからめる、 シンプルだけどめっちゃ美味しかったですよ〜 タレは2種類用意しました。 定番の甘辛醤油味と、塩キャラメル風^^ お芋だけで満腹になるほど食べました(笑) マツジュンさん、また来年も元気でお会いしましょう。 |
 |
Vol.81 (2018/10/13) キャンドル作り
 |
20数年来の友人、中村さんがとっておきのキットを提供して くださってキャンドル作りをしました。 ガラスの器に色の砂を入れて、飾り付けをして、溶かしたジェル を流し込むのです。 |
砂に模様をつけたり、ジェルにラメを混ぜ込んだり、ちょっとひと工夫(^^v
|
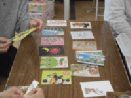  |
合間の時間に、しおりを作りました。 絵はがきを切ってマスキングテープで飾るだけなんだけど、オリジナル感バッチリ。 ”読書の秋”です。こんなしおりを作ったら、分厚い本が読みたくなるかも知れません・・・ |
Vol.80 (2018/7/14) アイスクリーム
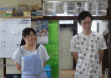 |
七夕と同じ(?!)年に1回に来てくださっている梨枝子さん 以前から気になっていたのですが、めでたくご結婚なさったとのこと(^^) アツアツのお二人が、冷た〜いアイスクリーム作りを教えてくださいました。 |
  |
まずはコーンカップの代わりに春巻きの皮を成形 してレンジでチンします。 板チョコを細かくして湯煎にかけ、柔らかくなったら 春巻きの皮に薄く流し入れます。 |
 |
| カップの準備ができたら、アイスクリーム にとりかかります。 卵と砂糖をよく混ぜて生クリームと牛乳 を合わせればOK これをペットボトルに1人分ずつ入れます。 |
  |
  |
ここからが、梨枝子さんプロデュースの楽しいところ!! 大きいフリーザーパックに氷と塩を入れて、そこに材料が 入ったペットボトルを入れてタオルに包み、ゴロゴロ転がす のです。つまり、人力アイスクリームメーカー(^^b ただの氷じゃ冷えないから、塩を入れて温度を下げると いうわけ。いきなり理科の実験みたいになりました。 外から触って固まって来たな、と思ったら、ペットボトルのキャップ を開けて、出来具合を確認します。
|
| ビスケットやカラースプレーで飾って出来上がり(^^v 急いで食べないと溶けちゃうから、あまりおしゃべりもしないで 食べちゃいました。 今回は贅沢に乳脂肪分の多い生クリームを使ったので、濃厚 な味になりましたが、植物性の生クリームを使えばさっぱり味に 仕上がるとのこと。 ハサミで切りやすいペットボトルを選ぶのもコツです。 早速夏休みに作らなくっちゃね! |
 |
Vol.79 (2018/5/12) オムレット
  |
パティシエの和(より)さんが 5年ぶりに来てくださいました。 「オムレットって”まるごとバナナ”の 皮だよね?」って聞いたら、「私も そう説明するよ」と笑っていました。 パンケーキとはちょっと違うフワフワ な口当たりが実現できるかな?! |
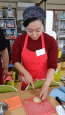 |
| 卵とお砂糖を合わせ、人肌程度に湯煎で温めて 泡立てるのがコツ。フワフワになるまで泡立てます。 小学生は電動のを使ったけどプロの技を見せて 欲しいとリクエストしたら、泡立て器だけで仕上げ てくれました。左手でボウルを回しながら右手も フル回転。さすが〜 |
  |
   |
| 低温のホットプレートでふっくら焼きます。 ホットプレートを3つ同時に使おうとしたら ブレーカーが落ちちゃってちょっと苦労した けど、何枚か焼くうちにだんだん上手に なりました。 |
  |
 |
野菜ジュースと缶詰の桃とヨーグルト で、スムージーも作りました。 材料を凍らせておくと、冷た〜く 出来上がります。 |
 |
  |
カスタードクリームも生クリームもたっぷり作りました。 果物もたくさん用意したから、お腹いっぱい食べちゃい ました (^0^) ホットケーキミックスでチャチャッと作るのとは違って 手間がかかったけど、ちゃんとフワフワな食感にでき あがって大満足! より先生、ぜひまた来てくださいね。  |
Vol.78 (2018/2/17) つるし雛作り
| 今回は、菊池美和子先生による 『伝承〜郷土民芸』 千代紙で「つるし雛」を作りました。 いつもより人数が少なくて寂しいかなぁと心配しましたが、 たくさんの材料から好きなものを選びたい放題で、それは それで楽しみました。 つるし雛の1つ1つの細工物には意味や云われがあって、 今回作ったのは 『三角』とか『三角火打』というもの。 昔、「薬袋」はすべて三角の形をしていました。この「三角」 には”病気に無縁でありますように”との願いが込められて いるのです。不運が起こらないように祈るお祓いとしての意 味もあるそうです。 千代紙を折って3枚組み合わせて1個の形になります。 折るのはそんなに難しくないのだけれど、とにかく数をたくさん 折らないと出来上がりません。 組み合わせるのは最初難しかったけど、形がわかったら小学 生でもできるようになりました。 |
 |
  |
柄の組み合わせも面白くて、こんなに ゴチャゴチャしてて大丈夫? と思った のも吊るしてみると華やかになりました。 地味にまとめたのはシックでオシャレな 仕上がりになったし、いろいろ試してみ たくなります。 |
折るのが出来たらリリアンのひもを束にして裾飾りにし、 間にビーズやストローを通してつなげます。 これも色によって出来映えが違って、個性が出ます。 折り紙は、ひとりで黙々と折ることもできるけど、お喋り しながらワイワイ作るのも楽しくて、和やかな時間を過 ごせました。菊池先生、今年もありがとうございました! |
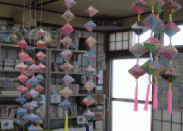 |
| ページトップへ |  |